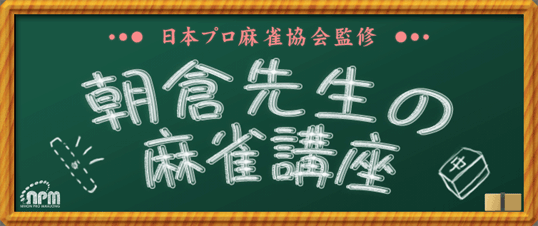こんにちはー(*^_^*)
日本プロ麻雀協会の朝倉ゆかりです。
トレーニングモード理論編の牌効率問題について解説をしていきます。
今回はチートイツ含みの問題に焦点を当てていきますね。
まずはこの問題です。
![]()
チートイツのイーシャンテンでもあり、難しそうですね。
候補としては![]() 、
、![]() 、
、![]() 、
、![]() 辺りでしょうか。
辺りでしょうか。
ではそれぞれのテンパイ種類と枚数を計算してみましょう。
![]() ・・・
・・・ ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(8種)
⇒8×4−8=24枚
![]() ・・・
・・・ ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(8種)
⇒8×4−7=25枚
![]() ・・・
・・・ ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(8種)
⇒8×4−10=22枚
![]() ・・・
・・・ ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(7種)
⇒7×4−5=23枚
この結果からこの牌姿では、
打 ![]() とするのがもっとも手広いイーシャンテンになります。
とするのがもっとも手広いイーシャンテンになります。
チートイツの可能性も残す、
打 ![]() や打
や打 ![]() は若干狭くなるのが意外ですね。
は若干狭くなるのが意外ですね。
ではこの問題はどうでしょう?
![]()
こちらもチートイツのイーシャンテンでもある手牌です。
候補は![]() 、
、![]() 、
、![]() 、
、![]() でしょう。
でしょう。
では計算してみましょう。
![]() ・・・
・・・ ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(8種)
⇒8×4−9=23枚
![]() ・・・
・・・ ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(7種)
⇒7×4−6=22枚
![]() ・・・
・・・ ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(7種)
⇒7×4−9=19枚
![]() ・・・
・・・ ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(7種)
⇒7×4−6=22枚
この手牌はシュンツ系に受けた時のマンズの受け入れである
![]() と
と ![]() がチートイツの受け入れとカブっているため、
がチートイツの受け入れとカブっているため、
チートイツと両天秤に受けた方が広くなるケースですね。
チートイツのイーシャンテンは、
通常受け入れが3種9枚とかなり狭いです。
面子手と複合して、尚且つ受け入れがカブっているときのみ、
チートイツも見た方が広くなる程度です。
どうしてもテンパイしたい局面では、
チートイツを狙わない方が良いと言われる理由はここにあります。
麻雀は牌効率をただ追うだけでは勝てません。
局面は常に変化し、
その時その時で打牌選択は変わりますし、
オリることもたくさんあるからです。
しかし牌効率という基礎を身につけて、
そこで初めて手役や点棒状況との兼ね合いができるのです。
牌効率をマスターし、
一打一打最高の期待値を導き出すことができれば、
一流の打ち手の誕生です!